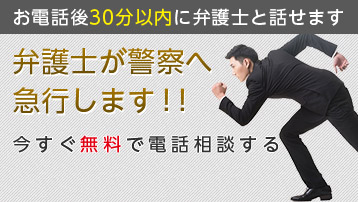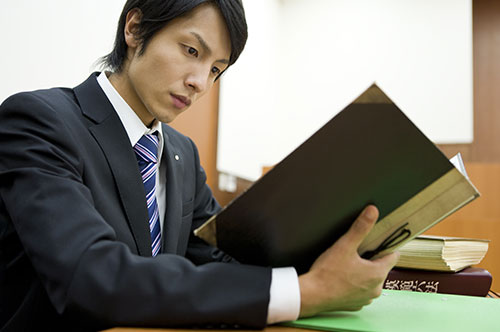不法就労助長罪の初犯で摘発されたら|経営者が知るべき対応策とは
- その他
- 不法就労助長罪
- 初犯

令和4年に東大阪市内で認知された犯罪件数は4051件で、そのうち検挙に至ったものは963件でした。
外国人に不法就労をさせた場合などには、不法就労助長罪で処罰されるおそれがあります。初犯でも重く処罰される可能性があるので注意すべきです。外国人労働者を雇用する事業者は、不法就労助長罪による摘発を防ぐため、在留資格の確認などを徹底しましょう。もし不法就労助長罪で摘発されてしまったら、速やかに弁護士へご相談ください。
本記事では不法就労助長罪について、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスの弁護士が解説します。
出典:「令和5年版 統計書」(東大阪市)


1、不法就労助長罪とは?
「不法就労助長罪」とは、就労が認められない外国人を雇い入れるなど、不法就労を助長する行為をした場合に成立する犯罪です。
-
(1)不法就労助長罪の目的
不法就労助長罪が定められているのは、外国人の不法就労によって日本国内の社会秩序に悪影響が生じる事態を防ぐためです。
外国人が日本に在留している間にできる活動の範囲は、在留資格によって明確に定められています。特に就労については、日本国内で提供されるサービスの質を確保することなどを目的として、能力などについて審査が行われたうえで在留資格が認定されています。
在留資格によって認められていない不法就労は、日本国内におけるサービスの低下や治安の悪化などにつながるおそれがあるため禁止です。
その規制の一環として、就労が認められない外国人を雇い入れるなど、不法就労を助長する行為も犯罪として処罰の対象とされます。 -
(2)不法就労助長罪の構成要件
不法就労助長罪は、以下のいずれかの行為をした場合に成立します(出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項)。
- ① 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせる
- ② 不法就労活動をさせるために、外国人を自己の支配下に置く
- ③ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為や、②の行為に関してあっせんをする
「不法就労活動」とは、在留資格によって認められていない就労や、不法入国者による就労などを意味します(同法第24条第3号の4イ)。
なお上記の各行為をした者は、不法就労活動に該当することを知らなかったとしても、そのことを理由に処罰を免れることはできません。ただし、過失がない場合を除きます(同法第73条の2第2項)。
2、不法就労助長罪に問われた場合に、事業に生じる影響
不法就労助長罪で摘発されると、刑事罰を受けるおそれがあるなど、事業に深刻な悪影響が生じてしまいます。刑事罰の内容や、実際に不法就労助長罪で書類送検された企業の事例を詳しく紹介しましょう。
-
(1)不法就労助長罪は、初犯でも重く処罰され得る
不法就労助長罪の法定刑は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」です。懲役と罰金が併科されることもあります。
特に、多数の不法就労者を雇い入れた場合などには、初犯であっても実刑判決を受けるおそれがあるので十分ご注意ください。 -
(2)不法就労助長罪で書類送検された事例
令和3年12月、カレーや和菓子の製造販売を行う老舗事業者とその従業員が、不法就労助長罪の容疑で書類送検されました。
本件において事業者は、ネパール人6名を不法就労させた疑いで書類送検されています。
ネパール人は、通訳などとしての就労が認められる「国際業務」の在留資格を有していました。しかし事業者は、在留資格外である、肉まんや菓子を製造する工場の作業員としてネパール人を働かせたとのことです。
なお最終的に、事業者と従業員はいずれも不起訴となったことが報道されています。 -
(3)実際に不法就労助長罪で有罪判決を受けた事例
書類送検にとどまらず、実際に不法就労助長罪で有罪判決を受けた例もあります。
東京地裁平成15年3月28日判決では、被告人がコロンビア人の未成年女性2名をストリップ劇場に紹介し、ストリッパーとしての雇用をあっせんした事案が問題になりました。
コロンビア人女性2名は不法残留中だったため、日本国内において就労することは不法就労活動に当たります。
被告人は過去に同種の犯罪行為をしており、罰金刑に処せられて反省の機会を与えられていました。しかしそのわずか1、2か月後には、不法就労の助長行為への関与度合いを各段に深めたことが認定され、悪質であると断罪されたのです。
また被告人は、公衆道徳上有害な業務について職業紹介を行ったものとして、職業安定法違反の責任も問われました。
東京地裁は、ストリッパーの業務が公衆道徳上有害であることを指摘したうえで、未成年の女性を平然とストリッパーとして紹介していた被告人は、規範意識が欠落していると厳しく非難しました。
上記の各事情を考慮して、東京地裁は被告人の刑事責任が相当に重大であるとして、懲役1年10か月の実刑判決を言い渡されています。 -
(4)刑事罰以外に生じ得る影響
刑事罰を受けずに済んだとしても、不法就労を助長した事実が報道されれば、企業としての評判が大きく傷ついてしまうでしょう。SNSなどで拡散されると、さらに企業へのネガティブな印象が拡大するかもしれません。
コンプライアンスに関する社会の監視は強まっているとも言えます。不祥事に発展させないため、不法就労を助長するような雇用やあっせんなどは慎みましょう。
お問い合わせください。
3、不法就労助長罪で摘発された後の流れと、適切な対応策
不法就労助長罪で摘発された場合の刑事手続きの流れは、在宅捜査が行われる場合(=在宅事件)と逮捕・勾留される場合(=身柄事件)で異なります。
もしも摘発されてしまったら、不起訴や量刑の軽減を目指すためにも、弁護士と協力しながら対応しましょう。
-
(1)在宅捜査が行われる場合の流れ
摘発をされても、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと、逮捕はされずに在宅事件として捜査が進みます。在宅事件の刑事手続きの流れは、以下のとおりです。
① 警察・検察による捜査
警察と検察から、証拠物の押収や参考人取り調べなどの捜査を受けます。罪を犯した疑いのある者(=被疑者)は後日警察署や検察庁に呼び出され、取り調べを求められます。
② 起訴・不起訴の決定
捜査の結果を踏まえて、検察官が被疑者を起訴するかどうかを決定します。不起訴であれば、その時点で刑事手続きが終了し、普段の生活に戻ることができます。
ただし、在宅捜査の場合、いつ起訴・不起訴の処分が行われるかは分かりません。
③ 刑事裁判
起訴された場合は、裁判所の公開法廷で有罪・無罪および量刑が審理されます。審理が熟した段階で、裁判所が判決を言い渡します。
控訴・上告の手続きを経て刑が確定し、実刑判決の場合は刑が執行されます。 -
(2)逮捕・勾留される場合の流れ
逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合は、身柄を確保されて操作が進みます。身柄事件の刑事手続きの流れは、以下のとおりです。
① 逮捕・起訴前勾留(警察・検察による捜査)
逮捕と起訴前勾留で、最長23日間にわたり身柄が拘束されます。その間、警察や検察は捜査を行い、被疑者は警察官や警察官の取り調べを受けます。
② 起訴・不起訴の決定
捜査の結果を踏まえて、検察官が被疑者を起訴するかどうかを決定します。不起訴であれば、その時点で刑事手続きが終了し、身柄が解放されて元の生活に戻ることができます。
身柄事件の場合、起訴前勾留の期間が満了する前に起訴処分または不起訴処分が行われることが一般的です。
③ 刑事裁判
在宅事件と同様で、裁判所の公開法廷により、有罪・無罪が審理されます。 -
(3)不起訴や量刑の軽減を目指すためには、弁護士への早期相談が大切
不法就労助長罪で摘発されてしまった場合は、不起訴処分や量刑の軽減を目指すために、早い段階で弁護士に相談することが大切です。
弁護士は、被疑者・被告人の良い情状を検察官や裁判所にアピールするなど、できる限り早期に刑事手続きから解放されるための対応を行います。起訴前の取り調べのアドバイスから、刑事裁判における弁護活動まで、一貫して被疑者・被告人をサポート可能です。
不法就労助長罪の疑いをかけられてしまったら、すぐに弁護士へご相談ください。
4、不法就労助長罪を疑われないための予防策
不法就労助長罪による摘発を避けるためには、以下の各点を意識した予防策を講じましょう。
-
(1)在留資格の確認を徹底する
外国人を雇用する際には、必ず在留カードの提示を求めて、在留資格を確認すべきです。自社が行う業務への就労が認められていない在留資格者や、不法残留者などであることが判明した場合は、その外国人を雇用してはいけません。
在留資格の確認に当たっては、以下のポイントに留意しましょう。① 在留カードのコピーは改ざんのおそれがあるため、必ず実物の在留カードを確認しましょう。
② 在留カード表面の就労制限の有無欄を確認します。確認フローは以下のとおりです。
- (a)「就労制限なし」なら雇用できます。
- (b)「就労不可」の場合は原則として雇用できません。ただし、資格外活動許可欄を確認しましょう。
- (c)一部就労制限がある場合は、制限内容を確認して判断します。また、資格外活動許可欄も確認しましょう。
③ 在留カード裏面の資格外活動許可欄を確認します。同欄において就労が許可されている場合は、在留資格の種類にかかわらず、同欄に記載された制限の範囲内で雇用できます。
④ 在留カードを所持していない場合は、旅券(パスポート)で就労の可否を確認します。在留資格が「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の場合は、資格外活動許可を受けていない限り雇用できません。 -
(2)不法就労助長罪につき、従業員に対して周知・教育を行う
不法就労助長罪は犯罪であり、加担すると刑事罰などのリスクがあることを、従業員に対して十分に周知しましょう。
特に外国人雇用に携わる人事担当者や、外国人を配属させる現場の管理職などには、不法就労助長罪のリスクを十分に周知・教育することが大切です。
5、まとめ
人手不足で大変な思いをしている企業もあるでしょうが、就労が認められていない外国人を雇用してはいけません。不法就労助長罪で処罰されるおそれがあります。外国人を雇用する際には、必ず在留資格を確認しましょう。
もし不法就労助長罪で摘発されてしまったら、一刻も早く弁護士に相談しましょう。ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスでは、刑事弁護に関するご相談を随時受け付けておりますので、ぜひお早めにご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています