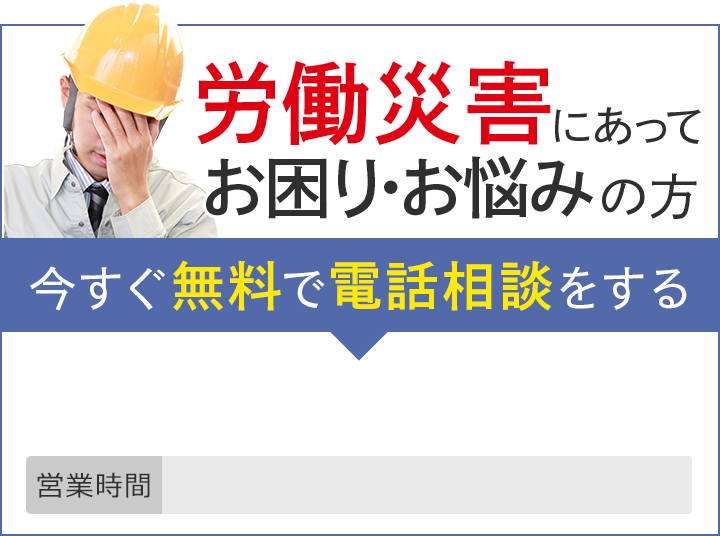労災保険は物損にも適用される? 補償範囲と損害賠償請求
- 慰謝料・損害賠償
- 労災
- 物損

大阪労働局の発表では、令和5年の大阪府内での労働災害による死傷者数は9218人(新型コロナウイルス感染症による死傷災害を除く)で、前年同期比で4.2%の増加が見られました。
労災事故に遭ってしまった場合、自分の身体だけでなく、眼鏡やスマートフォンなど私物の持ち物も損傷してしまうこともあります。自分の私物は労災保険の補償の対象になるのでしょうか?
自動車や着衣、持ち物などに発生した損傷・破損のことを「物損(物的損害)」といいます。労災保険は労働者の業務上または通勤中の負傷、疾病、障害、死亡に関する補償を行う制度ですが、物損には適用されません。
しかし、労災事故の状況によっては自動車保険が利用できる場合があります。また、加害者や会社に対して損害賠償請求できるケースもあるため、必ずしも事故による物損が補償されないとは限りません。
本コラムでは、労災保険の補償範囲や物損が補償されるケースなどについて、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスの弁護士が解説します。
目次
1、労災保険が補償する範囲
労災保険は、労働者の業務中や通勤中に生じた傷病や障害・死亡などに対して必要な補償を行う制度です。ただし、補償範囲は限定的であり、補償されない範囲もあることは理解しておく必要があります。
具体的な補償内容と物損に関する取り扱いについて確認していきましょう。
-
(1)労災保険で補償される範囲と内容
労災保険で補償されるのは、労働者本人の傷病・障害・死亡にかかわる損害が中心です。具体的には、以下のような費用が補償対象となります。
補償内容 概要 療養補償給付 労災事故によるケガや病気の治療に必要な費用の補償 休業補償給付 労災事故によるケガや病気で仕事を休業したときの補償 障害補償給付 労災事故によるケガや病気で一定以上の障害(後遺症)が残ったときの補償 介護補償給付 労災事故によるケガや病気で介護が必要な場合の補償 傷病補償年金 労災事故によるケガや病気で1年6か月以上治療を続ける場合の補償 遺族補償給付 労災事故によって死亡したときの遺族への補償 葬祭料・葬祭給付 労災事故によって死亡したときの葬儀関係費用の補償
労災事故によって受けた損害の程度によって、補償を受けられる範囲が変わります。
なお、労災保険は労働者本人の社会復帰の促進などを目的とした制度であるため、事故の相手方に対する補償は含まれません。 -
(2)物損は労災保険の補償範囲に含まれない
労災保険では労働者自身の傷病に関連する補償が中心となっており、物損は補償対象に含まれません。労働者災害補償保険法では、労災保険の保険給付の対象を「労働者の負傷・疾病・障害または死亡」と定めています。
第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。- 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
- 2 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害または死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)
- 3 労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
労働中に事故で自動車が損傷したり、眼鏡やスマートフォンが損傷したりした場合は、物損になるため労災保険からの補償は受けられません。
したがって、労災事故で物損が生じた場合には、ほかの補償手段を検討しましょう。
2、通勤災害の場合は自動車保険が適用される
通勤中に起きた通勤災害の場合は、労災保険だけでなく自動車保険が適用される場合があります。労災保険と自動車保険の違いや補償範囲について、以下で具体的に解説していきます。
-
(1)労災保険と自動車保険の違い
自動車保険には強制保険である「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があり、労災保険とは目的や補償対象が異なります。
保険の種類 補償対象 概要 労災保険 労働者の傷病・障害・死亡 労働中や通勤中の事故による労働者の傷病などを補償する制度 自賠責保険 人身事故の賠償損害 交通事故の被害者に対する最低限の補償を行う強制保険 任意保険 対人賠償・対償・対物賠償など
※契約内容によって異なる自賠責保険で補償されない範囲のリスクに備え任意で加入する自動車保険
労災保険は労働中や通勤中の事故による労働者の傷病などを補償する制度で、物損は補償範囲外です。自賠責保険はすべての自動車・バイクに加入が義務付けられている保険で、労災保険と同様に物損に対する補償は含まれません。
任意保険は自賠責保険でカバーできない範囲を補うために加入する自動車保険で、補償対象は契約内容によって異なります。 -
(2)任意保険に加入していれば物損も補償される可能性がある
通勤中に起きた労災事故の場合、加入している任意保険の契約内容によっては物損も補償されることがあります。特に「車両保険」を契約していれば、自分の車の損傷に対して保険会社から保険金を受け取ることが可能です。
任意保険に車両保険の契約が含まれていれば、自分の車が損傷したり故障したりした場合に保険金が支払われます。車両保険に加入していない場合は物損事故の補償を受ける手段が限られてしまうため、契約内容を確認してみてください。
なお、任意保険には「対物賠償保険」が含まれている場合が多いですが、対物賠償の補償対象は原則として「他人の財物」に限られます。眼鏡やスマートフォン、パソコンなどの自分の所有物に対する補償は受けられないため、注意が必要です。 -
(3)労災保険と自動車保険は併用できる
通勤災害の場合、労災保険と自動車保険(自賠責保険・任意保険)は併用できます。
ただし、同じ損害に対して二重取りできるわけではありません。労災保険と自動車保険で200%の補償を受けられるわけではなく、両方あわせて100%の補償までとなります。
たとえば、労災保険の休業補償給付で平均賃金の60%の補償を受けている場合、残りの40%は自動車保険によって受け取りが可能です。
労災保険と自動車保険、どちらか一方でしか補償されない項目もあるため、通勤中の事故の場合は併用することをおすすめします。
3、加害者や会社に請求できるケースも
労災事故に巻き込まれた場合は、加害者や会社に対して損害賠償請求ができるケースもあります。
労災保険は労働者の傷病による収入減などを補償する制度ですが、補償範囲は損失の一部に限られています。十分な補償を得るためには、加害者や会社に対する損害賠償請求が必要な場合もあるでしょう。
損害賠償請求できるケースや補償内容について、以下で解説していきます。
-
(1)加害者がいる場合は損害賠償請求が可能
第三者の過失が原因で労災事故に遭った場合、被害者は加害者に対して損害賠償請求ができます。請求できる内容は事故状況によっても異なりますが、代表的なものは以下の通りです。
損害賠償項目 概要 治療関係費 治療費・入院費・手術費・薬代・入通院交通費など治療に必要な費用 慰謝料 事故によって被った精神的苦痛に対する損害を補償する費用 休業損害 事故によって仕事を休んだ場合の損害を補償する費用 逸失利益 障害などが残り今後の仕事に影響を及ぼすことを補償する費用 車両に関する損害賠償 修理代や買い替え費用・代車使用料などの費用 着衣・持ち物などの損害賠償 修理代や物品ごとの時価額の賠償
スマートフォンやパソコンなどの物損の場合、賠償されるのは基本的に「時価額」が限度となります。時価額とは、同等商品の現時点の価格から、経過年数や使用による消耗分を差し引いた金額です。
修理が可能な場合は、時価額を超えなければ修理代がそのまま賠償されます。新品の価格を賠償してもらえるわけではないため注意しておきましょう。 -
(2)会社に損害賠償請求できるケースもある
事故が発生した背景に会社の落ち度(過失)がある場合、会社に対して損害賠償請求ができます。会社に損害賠償請求を行える可能性があるのは、以下のようなケースです。
- 安全配慮義務違反
従業員が安全に働ける環境を整える義務を会社が怠ったケース。たとえば、必要な安全教育を実施しなかったり、危険な作業に対する保護具を用意しなかったりした場合です。 - 使用者責任
従業員が仕事中に他人に損害を与えた場合、その従業員を雇用している会社にも責任があるとされるケース。たとえば、社用車での事故や、従業員の作業ミスによる事故などが該当します。 - 工作物責任
会社が所有・管理している建物や機械設備の欠陥により事故が起きた場合の責任。たとえば、建物の老朽化による部材の落下事故や、メンテナンス不足による機械の故障事故などが該当します。
これらの場合の損害賠償請求の内容は、加害者個人に対する請求と同様です。加害者や会社への損害賠償請求には複雑な手続きがともなうため、必要に応じて弁護士に相談することをおすすめします。
- 安全配慮義務違反
4、損害賠償請求は弁護士へ相談を
労災事故で加害者や会社に対して損害賠償を請求する際は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士へ相談するメリットは、以下のとおりです。
-
(1)事故の相手や会社との示談交渉を任せられる
弁護士には、事故の相手や会社との示談交渉を任せられます。
損害賠償を請求するには、請求相手と示談交渉を行わなければなりません。いくら請求できるのか、またスムーズに支払ってもらえるのかなど、さまざまな不安や疑問が生じるでしょう。
弁護士が代理として交渉にあたることで、適切な条件での解決を目指せます。被害者の負担を軽減できるほか、交渉で不利な立場になってしまうのを防げるのもメリットです。 -
(2)適切な損害賠償を受けられる可能性が高まる
弁護士に相談することによって、適切な損害賠償を受けられる可能性が高まります。
特にケガや病気・傷害などが生じた場合の慰謝料は、算定基準によって金額が大きく異なる可能性があります。弁護士に依頼すれば、もっとも高額な慰謝料となりやすい弁護士基準で算定が可能です。
請求相手から提示された示談金や損害賠償金に納得できない場合は、弁護士への相談を検討してみてください。 -
(3)裁判に発展した場合もサポートできる
弁護士は、労災や損害賠償請求に関する裁判を起こす場合にも総括的なサポートが可能です。
示談交渉は裁判よりも早期に問題を解決できる方法ですが、あくまでも双方の合意が前提となります。請求相手が責任を負う気がなかったり、双方の意見が合わなかったりして決裂するケースもあるでしょう。
そのような場合に交渉以外の方法で解決を目指すには、裁判を検討する必要があります。裁判手続きでは、示談交渉以上に客観的な証拠や法的根拠が重視されます。
手続きも複雑になるため、交渉が難航している場合には早めに弁護士へ相談することが望ましいです。
お問い合わせください。
5、まとめ
労災事故による物損(眼鏡やスマートフォンの破損など)は、労災保険の補償対象外です。
しかし、マイカー通勤中の事故であれば自動車保険が適用され、物損の補償を受けられる可能性があります。また、第三者や会社側に責任がある事故の場合は、物損に対する損害賠償請求も可能です。
労災事故に関する補償や会社との交渉、損害賠償請求についてお悩みの場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。事故後の対応は負担となりやすいですが、弁護士への相談によって効率的に手続きを進められるでしょう。
損害に対する適切な補償を受けるためにも、ぜひベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスの弁護士にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|