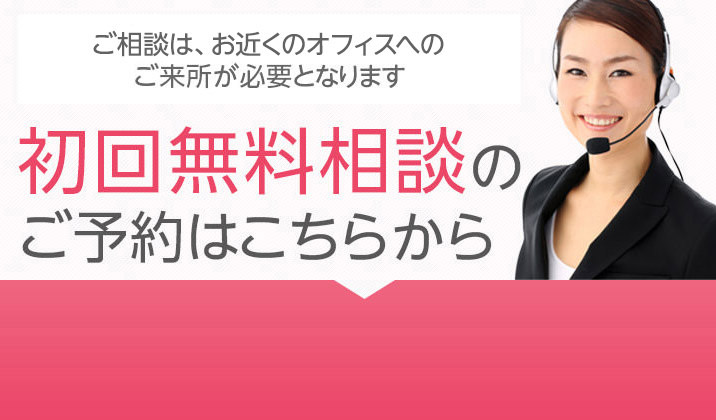家を建ててすぐでも離婚できる? 対処法や注意点を弁護士が解説
- 離婚
- 家建てて
- 離婚

マイホームの入手の際、意見が衝突したり、将来の生活への不安が浮き彫りになったりして、新築後に夫婦仲が悪化したり、離婚に至るケースがあります。
家を建ててすぐの状況でも離婚はできますが、住宅ローンや家の処分など、注意すべきポイントがあります。
今回は、家を建ててすぐに離婚する場合の家の処分方法や注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスの弁護士が解説します。


1、家を建ててすぐでも離婚できる?
そもそも家を建ててすぐに離婚することができるのでしょうか。
-
(1)家を建ててすぐに離婚することを「新築離婚」という
家を建ててすぐに離婚することを「新築離婚」といいます。
新築離婚の原因は、マイホームを建てる際の意見の衝突や、夫婦仲の悪化です。
家を建てる際には、立地、ハウスメーカー選び、間取り、設備、インテリアなど決めるべき事項が多岐にわたりますので、それらを夫婦で話し合って決めていかなければなりません。
その際に夫婦で意見の衝突が起きると、夫婦仲が悪化し、「このまま結婚生活を続けても大丈夫だろうか……」と、お互いの価値観の相違に気付くこともあるでしょう。 -
(2)お互いの合意があれば家を建ててすぐでも離婚できる
夫婦の話し合いによって双方が離婚に合意すれば、家を建ててすぐであっても離婚することができます。
このように、話し合いで離婚に至ることを「協議離婚」といいます。
協議離婚が成立しない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立てをし、「調停離婚」を目指すことになります。調停も基本的には話し合いの手続きですので、お互いに離婚の合意に達すれば、家を建ててすぐであっても離婚は可能です。
しかし、調停が不成立になると離婚訴訟の提起が必要になります。離婚訴訟では、法定離婚事由がなければ離婚は認められません。新築離婚の原因の多くが価値観の相違によるものですので、そのような理由だけでは離婚は難しいでしょう。
そのため、家を建ててすぐに離婚する場合は、協議離婚や調停離婚により離婚成立を目指していくことになります。
なお、家の建築中に離婚が決まったとしても、夫婦の個人的な事情になりますので、工事の中止は難しいといえるでしょう。
2、離婚前に建てた家はどうする? 家の処分方法
離婚前に建てた家はどうすればよいのでしょうか。以下では、家の処分や活用方法について説明します。
-
(1)売却して代金を分ける
離婚後、夫婦のどちらも離婚前に建てた家に住むことを希望しない場合には、家を売却することを検討します。
ただし、家を売却する際には、オーバーローンとアンダーローンで対応が変わりますので注意が必要です。・オーバーローンの場合
オーバーローンとは、住宅ローンの残高が家の評価額を上回っている状態をいいます。
オーバーローンの家を売却し、住宅ローンの返済に充てたとしても住宅ローンが残ってしまいますので、引き続きローンの返済を続けていかなければなりません。
・アンダーローンの場合
アンダーローンとは、住宅ローンの残高が家の評価額を下回っている状態をいいます。
アンダーローンの状態であれば、売却益を住宅ローンの返済に充てて、残りの売却代金を財産分与として夫婦で分けることができます。 -
(2)夫婦どちらかが住み続ける
家を建ててすぐに売却しても、立地などの条件によってはオーバーローンになるケースが少なくありません。そのため、売却ではなく、夫婦のどちらかが家に住むことも選択肢のひとつです。
① 住宅ローンの名義人が家に住む場合
住宅ローンの名義人が引き続き家に住むのであれば、特に手続きは必要ありません。そのまま家に住み、住宅ローンの支払いをしていくことになります。
なお、オーバーローンであれば、家は財産分与の対象には含まれませんので、財産分与で家を失う心配もありません。
② 住宅ローンの名義人でない人が家に住む場合
住宅ローンの名義人が家を出ていき、名義人以外が引き続き家に住むというパターンです。
たとえば、夫が名義人として購入した家に、妻と子どもだけが住み続ける場合が考えられます。この場合、夫は、別の場所で生活をするため、家賃の支払いに加えて住宅ローンの支払いをしなければなりません。
これを回避するには、住宅ローンの名義を夫から妻に変更する必要がありますが、住宅ローンの名義変更については金融機関の承諾が必要となり、容易ではありません。また、妻の返済能力によっては住宅ローンの借り換えも困難です。 -
(3)賃貸物件として貸し出す
夫婦のどちらも家に住むことを希望せず、売却してもオーバーローンで利益が出ないという場合には、賃貸物件として第三者に貸し出すことを検討してみましょう。
賃貸物件として貸し出す際の家賃と住宅ローンの返済額が同程度であれば、家に住まなくても住宅ローンの負担はなく、将来的な財産として残すことができます。 -
(4)夫婦どちらかが賃貸として住み続ける(リースバック)
リースバックとは、不動産会社やリースバック業者に家を売却し、同時に賃貸借契約を締結することで、家賃を支払いながら自宅に住み続けることができる方法です。
たとえば、妻が子どもと一緒に自宅に住みたいという希望があるものの、妻の収入では住宅ローンの名義変更や借り換えが困難なケースでリースバックが活用できます。
ただし、リースバックの売却金額は相場より低くなることが多く、結果として負担が増えるケースも少なくありません。売却の相場やローン残高、収入などを鑑みて慎重に判断しましょう。
3、家を建てて離婚する場合の注意点
家を建ててすぐに離婚する場合には、以下の点に注意が必要です。
-
(1)名義変更をするのか、住宅ローンの返済手順を話し合う
家を建ててすぐに離婚する場合、売却理由により、オーバーローンになるケースが多いでしょう。
オーバーローンでは、住宅ローンが残るため、引き続き名義人が住宅ローンの返済をしていかなければなりません。この場合、以下の事項を明確にしておくことが大切です。- 引き続き家に住み続けるか、売却するか
- 売却する場合、残ローンはどちらが払うか
- 住み続ける場合、名義人が住むか
- 名義人以外が住む場合、住宅ローンは誰が負担するか
このような事項を曖昧にしたまま離婚をすると、後々トラブルになるリスクがあります。特に財産分与や親権問題も絡む場合は、早めに離婚問題の実績が豊富な弁護士に相談することが大切です。
-
(2)家の取り決めは公正証書に記載する
夫婦間で家に関する取り決めをしたときは、書面に残しておくだけでなく、公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公文書で、当事者間で作成する私文書に比べて高い信用性を有する文書になります。また、金銭の支払い義務が含まれている場合には、執行認諾文言付きの公正証書にしておくことで、万が一、金銭の支払いが滞ったとしても、裁判をすることなく直ちに強制執行することができます。
お問い合わせください。
4、新築離婚を弁護士に相談するメリット3つ
新築離婚を弁護士に相談するメリットとしては、主に以下の3つが挙げられます。
-
(1)相手との交渉がうまく進まない場合、間に入り適切な対応を期待できる
弁護士は、代理人として相手との交渉を行うことができます。そのため、当事者同士では交渉がうまく進まない場合でも、弁護士が代理で交渉することで、取り決めがスムーズに決まることが期待できます。
新築離婚では、自宅の扱いが争点になりますので、法的観点から適切な解説をするためにも、離婚問題の実績が豊富な弁護士の協力が欠かせません。 -
(2)離婚協議書や公正証書などの法的文書の作成サポートを受けられる
夫婦の話し合いにより離婚の合意がまとまったときは、口頭での合意で終わらせるのではなく、必ず離婚協議書を作成するようにしてください。
弁護士に依頼をすれば、離婚協議書や公正証書の作成をサポートしてもらうことができますので、離婚後のトラブルを回避できる可能性が高くなります。本人同士でも離婚協議書の作成は可能ですが、知識や経験に乏しい一般の方では、記載漏れや曖昧な内容となりトラブルの原因となりますので、弁護士に任せた方が安心です。 -
(3)財産分与をスムーズに進められる
新築離婚では、自宅の財産分与が争点になります。
オーバーローンであれば自宅が財産分与の対象になることはありませんが、アンダーローンであれば自宅の評価額と住宅ローンの残額の差額が財産分与の対象になります。離婚後、自宅をどうするのか、誰が自宅に住むのかなどによって財産方法が変わってくるなど非常に複雑な問題になります。
そのため、スムーズに財産分与を進めるためにもまずは弁護士に相談した方がよいでしょう。
お問い合わせください。
5、まとめ
家を建ててすぐでも夫婦双方の同意があれば離婚することができます。また、家の処分・活用方法としては、「売却する」「どちらかが住み続ける」「賃貸物件として貸し出す」などの方法が考えられます。
弁護士に相談することで、新築離婚にまつわる交渉がスムーズに解決する可能性が高まります。新築離婚をお考えの方は、離婚問題の解決時実績が豊富なベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています