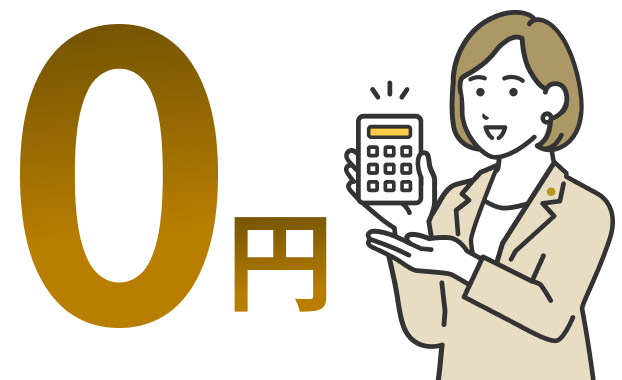登記義務化と罰則|効率よく相続登記を進める方法はあるのか
- 相続登記
- 登記
- 義務化
- 罰則

令和6年(2024年)4月1日から相続登記の義務化が開始されました。
不動産を相続し、所有者となった場合には、相続開始から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料に科されることがあります。また、令和6年4月1日以前に相続済みの不動産も対象になるため、相続して登記をしたかどうかできるだけ早く確認し、相続登記の手続きをする必要があります。
そこで今回は、相続登記義務化や効率よく相続登記を進める方法について、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスの弁護士が解説します。


1、登記義務化とは?
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。今回の改正で登記をしない場合の罰則も規定されたため、相続登記の基礎知識から確認しておきましょう。
-
(1)相続登記とは
相続登記とは、相続により不動産を取得することになった場合に、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きをいいます。
そもそも登記とは、土地や建物の所在や面積に加えて、所有者の住所・氏名を登記簿(公が管理する帳簿)に記載し、一般公開することをいいます。登記によって、権利関係や所有者の状態について誰にでもわかるようにし、詐欺や所有者でない第三者との取引などのトラブルを防止し、取引が円滑かつ安全に進められるようにすることが可能です。登記簿は、法務局に保管されており、誰でも閲覧できます。 -
(2)相続登記が義務化された理由
相続登記が義務化に至ったのは、「所有者不明土地」が増え、全国で問題となっていることが大きな要因です。
令和4年度(2022年度)の調査では、不動産登記簿のみで所有者の所在が判明しなかった土地の割合は24%(令和4年度国土交通省調べ)で、これは九州の土地面積よりも広いといわれています。
古い建物の倒壊や雑草の放置による、周辺の環境や治安の悪化などの問題が発生しても、所有者がわからない土地に対しては、近隣の住民も役所も対処することができません。
また、土地の売買や賃貸には、所有者全員の同意が必要になるため、所有者が不明の場合、公共事業や市街地開発などの用地の買い取り交渉ができず、土地の有効活用の妨げになり、深刻な社会問題となっていました。
これらの問題を解決するために法律が改正され、相続登記が義務になったのです。 -
(3)義務化の対象になる不動産
相続登記の義務の対象になるのは、土地や建物などの不動産です。登記義務化は、令和6年4月1日から開始されていますが、それ以前に相続された不動産も対象になっています。
また、遺産分割が成立した場合や、被相続人から遺贈された場合も対象になります。
つまり、相続によって取得した土地や建物などの不動産すべてが義務化の対象です。そのため、過去に相続で取得した不動産についても相続登記をしなければなりません。
ただし、相続登記の義務は、特定の不動産を相続で取得したことを知った日から開始されるというルールになっているため、被相続人の死亡や所有する不動産の存在を知らなかった期間については、相続登記の義務は生じません。
2、相続登記を行わなかったときの罰則は?
今回の改正により、期日までに相続登記を行わなかった場合、罰則として「過料」が科される可能性があります。過料とは、行政上の秩序を維持するために、違反者に少額の金銭的負担を科すものです。刑事事件の罰金である「科料」とは違い、前科になることはありません。
相続登記を期日までに行わなかった場合の過料について詳しくみていきましょう。
-
(1)過料の金額
相続登記をしない義務違反があった場合には、10万円以下の範囲内で過料が科されます。
-
(2)過料の対象となる場合
過料の対象は、不動産を相続で取得したことを知った時期によって異なります。
- 令和6年4月1日以降に知った場合
義務化が開始されてから不動産を相続で取得したことを知った場合には、相続登記をしない正当な理由がない限り、知った日から3年以内に相続登記をしなければ、過料の対象になります。
また、遺産分割によって所有権を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に登記しないと過料が科されます。 - 令和6年4月1日以前に知った場合
令和6年4月1日までに不動産を相続で取得していた場合には、相続登記をしない正当な理由がない限り、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をしなければ、過料の対象になります。
- 令和6年4月1日以降に知った場合
-
(3)相続登記を行わない「正当な理由」とは
法務省によると、以下の①〜⑤の場合には正当な理由があると認められます。
- ① 相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
- ② 相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
- ③ 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
- ④ 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
- ⑤ 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
参考:「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(法務省)
上記の①〜⑤をみると、相続人がたくさんいて、登記名義人を確定することが困難な場合や相続争いで所有者がまだ決まっていない場合、病気や経済的に困窮している場合には、「正当な理由がある」と判断される可能性が高いです。 -
(4)過料が科されるまでの流れ
期日を過ぎても相続登記がされない場合、登記官が義務違反を把握し、義務違反者に登記するように催告します。つまり、法務局から自宅に登記するように催告書が手紙で届くことになります。
そして、催告書に記載された期限内に登記されない場合には、登記官は裁判所に対して申請義務違反を通知します。ただし、催告を受けた相続人に登記申請を行わないことについて正当な理由があると認められた場合には、登記官は申請義務違反の通知を行いません。
裁判所に申告義務違反の通知が行われると、過料の対象になるか、裁判所が判断します。その結果、対象になるとの判断がされると、過料を科す決定がされ、義務違反者の手元に過料を支払うよう通知が来ることになります。
3、所有者不明の土地が含まれている場合の対応方法
相続登記をしたくても、所有者不明の土地が含まれていてできない場合はどうすればいいのでしょうか?
所有者不明の土地とは、
① 相続登記が行われていないため土地の所有者が判明しない土地
② 不動産の所有者の現住所が不明で所有者と連絡がとれない土地
のどちらかにあたる場合のことをいいます。
所有者不明の土地がある場合、現在利用しているかどうかによって対応方法が変わります。
-
(1)所有者不明の土地を利用している場合
登記上、所有者が判明していないが、現在その土地に住んでいる場合には、戸籍謄本などから相続関係を整理し、所有者を確定する必要があります。そして、自分の名義に相続登記を変更し、今後も利用することになります。
しかし、複雑になってしまった権利関係を整理するのは難しく、時間もかかります。一度弁護士に相談し、権利関係を整理することができないか聞いてみましょう。 -
(2)所有者不明の土地を利用していない場合
利用していない土地について、自分も所有者のひとりであることはわかっていても、他に誰が所有者なのかわからない場合、手続きがはじめられません。そのため、上記のケースと同様に、まずは権利関係を整理する必要があります。そして、不要な土地であるなら「相続土地国庫帰属制度」の活用を検討してみましょう。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を手放し、国に帰属させる制度です。しかし、これらいずれかにあてはまると制度を利用することができません。- ① 建物がある
- ② 担保権や使用収益権が設定されている
- ③ 他人の利用の予定がある
- ④ 特定有害物質によって土壌汚染されている
- ⑤ 境界が明らかでない土地、所有者の存否や範囲に争いがある
加えて、制度を利用する際には、土地管理費用の10年分相当の負担金を納付する必要があります。そのため、継続的に発生する固定資産税などと比較して、利用するメリットがあるかどうかを考えてみましょう。
-
(3)期限内に相続登記が難しい場合は「相続人申告登記」という制度も
所有者不明などの理由から期限までに申請が難しいという方のために、簡易的に相続登記の義務を履行できる「相続人申告登記」という制度が創設されています。期限内に相続登記が難しい場合はこちらの制度の利用も検討するといいでしょう。
相続人申告登記では、相続人同士の相続分の割合が確定していない土地でも、特定の相続人が単独で申請し、相続登記の義務を履行することが可能です。
ただし、権利関係を第三者に証明できるものではないため、その不動産の売却や抵当権の設定などをすることはできません。また、遺産分割が成立した場合は、通常の相続登記の手続きが再度必要になります。
一時的に過料を回避するための制度として認識しておきましょう。
4、効率よく相続の対応を進める方法
相続登記の義務化に伴って、期日までにすみやかに相続の手続きを進める必要があります。しかし、登記の手続きは調査や協議、書類の準備など難しい手続きが多数あり、なかなか思うように進まないことがあります。
そこで、効率よく相続の対応を進める方法について紹介します。
-
(1)相続人・相続財産を調査する
相続することになったらまず、相続人になる人を確定する必要があります。役所で戸籍謄本等を取り寄せて、過去の婚姻歴なども含めて相続人となる人全員を明確にしなければなりません。このとき、相続人になるはずの人を見逃してしまうと、遺産分割協議が無効になってしまうおそれがあります。
次に相続財産の調査が必要です。相続財産は、土地や建物などの不動産、車などの動産、預貯金、株式などプラスの財産だけでなく、借金や負債などのマイナスの財産も含まれます。すべての相続財産を調査した上で、相続するかどうかを判断することになります。
仮に借金があり、相続しないことにした場合には、相続開始から3か月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。そのため、相続人や相続財産の調査が難しい場合には、早めに弁護士へ調査や今後の手続きの方法について相談するのがおすすめです。 -
(2)遺産分割協議をする
相続人が確定し、相続財産が判明したら、相続人全員で誰がどの財産をどのくらい相続するのか、話し合う必要があります。遺産分割協議には、期間の制限がありませんが、相続登記が義務化されたことからも四十九日前後には話し合いをはじめるようにしましょう。
遺産分割協議が終わるまで、相続財産はいつまでも相続人全員の共有状態のままです。そうすると、全員の名前で登記することになり、権利関係が複雑になってしまいます。そうなることを避けるためにも、少しでも早く遺産分割協議を終わらせて、所有者を確定させましょう。
また、相続開始から10か月以内に相続税の申告・納税が必要なため、早い段階で遺産分割協議をし、相続登記まで済ませることをおすすめします。 -
(3)手続きが難しい・進まない場合には弁護士に相談する
遺産分割協議がうまく進まず、もめてしまうケースもあります。そのような場合には、相続人同士だけで話し合いを継続するのではなく、一度弁護士に相談してみましょう。弁護士であれば、法律に基づき適切な遺産分割を提案することができます。
また、相続財産の負債の割合によっては、相続放棄などの法的な手続きをした方がいい場合もあります。さまざま事情に合わせたアドバイスができるのも弁護士に相談する大きなメリットです。
加えて、相続登記だけなら行政書士にも可能ですが、遺産分割協議の途中でトラブルが発生した場合に、行政書士では対応することができません。弁護士に依頼することでトラブルを未然に防止し、起こってしまったとしても適切に対応してもらうことができます。
お問い合わせください。
5、まとめ
相続登記の義務化によって、不動産を相続したら必ず登記手続きが必要になりました。また、これまで登記せずに放置していた不動産についても申請の義務があります。相続開始や遺産分割から3年経過すると罰則として10万円以下の過料が科されることもあるので、すみやかに対応をはじめましょう。
権利関係が複雑になってしまった不動産でも弁護士であれば、調査し、手続きを進めることが可能です。登記や相続でお悩みの方はベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスの弁護士へぜひお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|